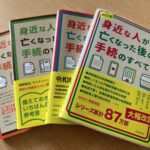相続人が海外に住んでいる場合は、相続手続きに必要な書類が通常と異なります。
日本国籍のある・なしに分けて、見ていきます。

日本国籍のある相続人の方
海外に住んでいて、日本国籍のある相続人の方は
印鑑証明書にあたる署名証明書と、住民票にあたる在留証明書の取得が必要です。
平日日中に本人が大使館などに出向き申請する必要はありますが、原則当日に発行してもらえます。
署名証明書
「署名証明書」は、通称「サイン証明」とも呼ばれ
本人が領事の前で署名したことを証明してくれる、印鑑証明書の代わりになる書類です。
居住している国の日本大使館か領事館で発行してもらえます。
通常、首都にあるのが大使館で、それ以外の都市にあるのが領事館です。
署名証明書には、貼付型と単独型の2種類があり
貼付型は、遺産分割協議書など証明したい書類に、直接証明書が割印されるため信頼度は高いです。
しかし、証明が必要な書類が生じる都度、本人が出向き取得するため、手間がかかります。
一方、単独型は、本人の署名だけを単独で証明する、まさに印鑑証明書のようなものです。
複数通取得でき、また、手続き後に原本を返してもらえる場合は、別の手続きにも使えて便利です。
通常、金融機関の手続きは単独型で済み、不動産の相続登記では貼付型を求められることが多いですが、実際に手続きする際は、事前に金融機関や法務局、司法書士に確認しておきましょう。
なお、日本に一時帰国する予定のある方は、貼付型なら日本の公証役場でも発行してもらえます。
在留証明書
次に「在留証明書」は、本人の住所がどこなのかを証明してくれる、住民票の代わりになる書類です。
これも、居住している国の日本大使館か領事館で発行してもらえます。
日本に住民登録がなく、かつ、現地に3か月以上滞在し居住していること、または、今後3か月以上滞在する見込みがあれば、申請できることになっています。
なお、この在留証明書を不動産の相続登記に使う場合は、在留証明書に本籍の記載が必要になり、
その場合は申請時に日本の戸籍謄本を用意しなければなりません。
日本国籍のない相続人の方
宣誓供述書
海外に住んでいて、日本国籍のない相続人の方の場合でも
大使館が例外的に
「署名証明書」と「在留証明書」の代わりになる「居住証明」を発行してくれる場合があります。
しかし、それらの発行が受けられない場合は
自分で「宣誓供述書」という書類を作り、その宣誓供述書の中で
氏名、生年月日、住所、そして、自分が被相続人の相続人である旨を述べ、署名をします。
それを、現地または日本の公証人に公証してもらえば
住民票・印鑑証明書・戸籍を兼ねられる書類として効力をもちます。
ただし、宣誓供述書は私文書なので、実際の相続手続きに支障がでないか
事前に司法書士などの専門家に内容を確認してもらった方が安心だと思います。
国籍について
実際のご相談では、国籍についての理解があいまいなことが多いです。
日本人が外国籍の方と結婚し、相手の国の国籍を選ぶと、日本の国籍は自動的に失われます。
日本の戸籍がそのまま残っているからといって、日本国籍があることにはならないのです。
(この場合は日本国籍喪失の届出が必要ですが、実際にはしていない方も多いです)
相続が発生してから慌てないよう、事前に確認しておきましょう。