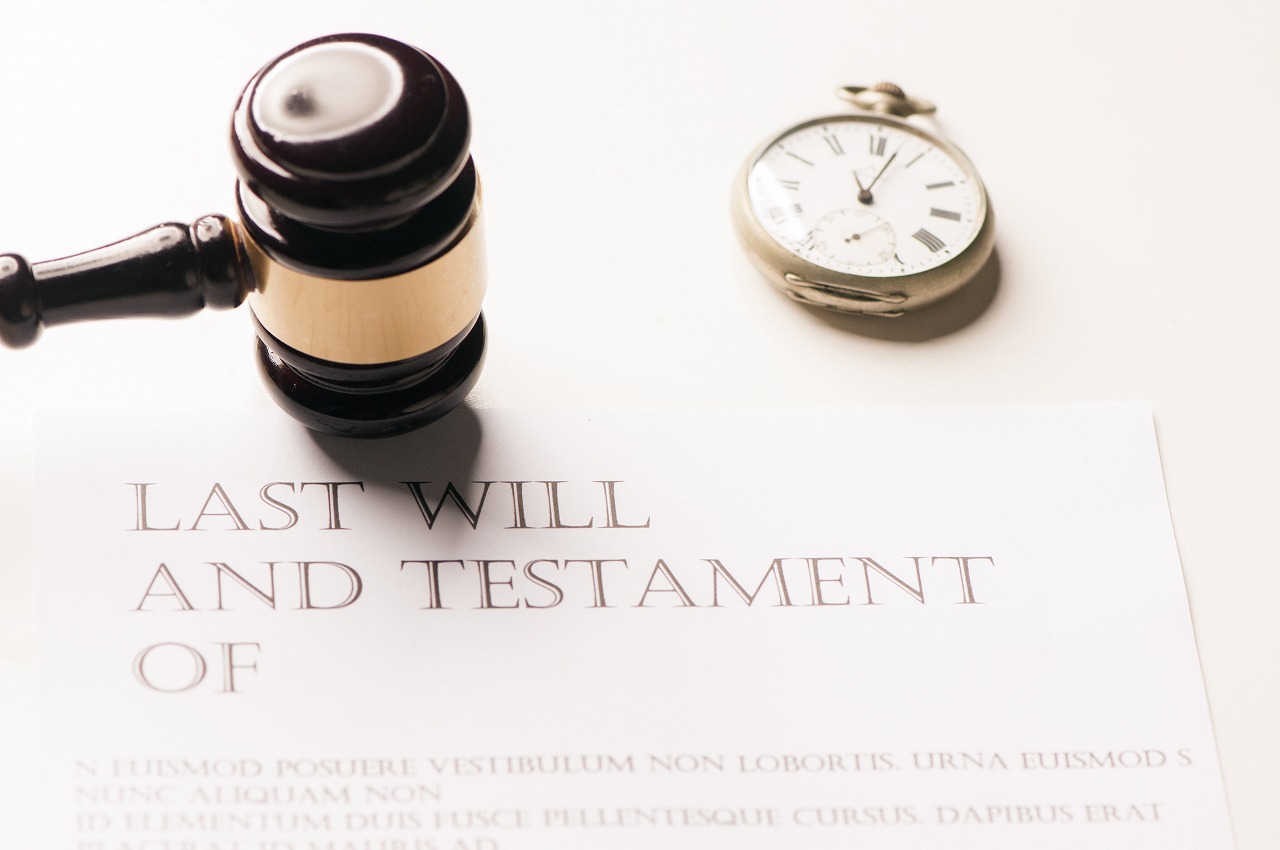
前回のコラムでは、親より先に子が亡くなり、さらに養子がいた場合、相続人や相続分、相続税の計算がやや複雑になるとお話しました。
でも、親子の間でこの世を去る順番が逆転することは、決してめずらしくありません。養子がいてもいなくても、財産を残す側・もらう側の両方がそれなりの年齢だったなら、「もらうはずの人が先に亡くなる」かもしれないと、遺言書を書くときにも頭の隅に置いておく必要があります。
ケース:母より先に長男が亡くなった場合
例えば、母が「同居している長男に全財産を相続させる」という遺言書を書きました。母の法定相続人は、この長男と別居している次男の2人だとします。
不幸にも、母より先に長男が亡くなって、その後、母が亡くなったとしたら、母の財産は次のどちらの方法で相続するのが正しいでしょうか(遺留分の問題は無視します)。
方法(1) 長男の子が、全財産を相続する
方法(2) 長男の子と次男が、法定相続分の2分の1ずつ相続する
従来は
・ 母の遺言書に基づき、母が財産を残したいと思っていた長男の相続人である長男の子が、全財産を相続する権利がある【方法(1)】
・ 遺言書は無効であり、長男の相続人である長男の子と次男の両方が、それぞれ法定相続分の2分の1ずつ財産を相続する権利がある【方法(2)】
この両方の見解がありました。
「相続させる遺言」についての最高裁判決
通常、遺言書を書いた人が亡くなる前に、遺言書で財産を受け取ることになっていた人が亡くなった場合には、その遺贈は無効となり、財産は相続人に帰属します。
しかし、相続人である長男に対し「相続させる」と遺言書に書かれているなら、長男の子が遺言書の内容を引き継ぐ権利があるのではないかと言われていたのです。
この「相続させる遺言」については、平成23年2月22日に【方法(2)】と考えるという最高裁の判決がありました。
通常、遺言書を書く人は、自分と相手との身分や生活関係、相手の資産その他の経済力、その財産との関係性などを考えた上で、誰に何をいくら残そうかを決めているはずです。
母の意思は、特定の相続人である長男に財産を残そうということだけで、長男の子にすべての財産を残そうとまでは考えていないと判断されたのです。
「予備的遺言」の記載
ただし母が、「同居している長男に全財産を相続させる」と書いた後に「ただし、長男が自分より先に死亡した場合には、長男の子に全財産を相続させる」と書いていたなら話は別です。
長男の妻や子が母と同居し面倒をみてくれていた場合など、次男ではなく長男家族に財産を残したいときには、「もしもの場合の遺言」、つまり「予備的遺言」の記載をしておくことも必要です。
遺言書は、前提条件が変わった都度、書き換えるのが一番です。でもそのときには、認知症を患うなど遺言能力に欠ける状況だということもあり得ます。
「簡潔に、でも、できるだけ細かく」なので、専門家に依頼した方が安心かもしれませんね。







