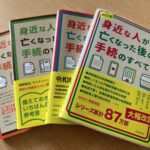デジタル遺言制度の検討が始まっています
日本経済新聞 2023年5月6日
「デジタル遺言」制度創設へ
ネットで作成/押印・署名不要 改ざん防止、相続円滑に
一般的な遺言の方式には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。
遺言は亡くなった方の最後の意思。
適切な遺言が残されていれば、相続争いは起きにくくなります。
ただ、遺言を作るのは通常、高齢の方なので
自筆証書遺言の本文をミスなく手書きするのはとても大変ですし
公正証書遺言は、公証役場に出向く手間や費用がハードルになっていました。
法務省では以前から
自筆証書遺言のデジタル化の検討が進められていましたが
第2回 デジタル基盤ワーキング・グループ 議事次第 令和4年3月1日(火)
このたび新たに
インターネット上で遺言を作ったり、保管したりする制度をつくるため
民法の改正をめざすとのこと。
令和6年3月を目処に、制度の方向性が示される予定だそうです。
デジタル化のメリット・デメリット
ちなみに今の制度でどのくらいの人が遺言を作っているかというと
年間の死亡者数が144万人(令和3年)なのに対し
死後の自筆証書遺言の検認件数は、年2万件弱(令和2年)にすぎません。
※公正証書遺言は、死後の公的手続きが不要なのでデータがありません。
また、生前に遺言を作成している方の数は
自筆証書遺言の保管制度を使って法務局に遺言を預けた人は、年17,000人弱、
公正証書遺言を作成した人は、年12万人弱となっています。
将来的にデジタル遺言がスタートし
ネット上のフォーマットに沿って入力していくような形になれば
素人でも作りやすくなるので、遺言を作成する人は増えるでしょう。
ブロックチェーンの技術を使えば、改ざんリスクもなくなり、安心です。
ただ、遺言の効力が生じるのは遺言者の死後なので
たとえ遺言者が認知症ではなかったとしても
遺言の内容が「本当に本人の意思なのか」が争いになる可能性は残ります。
生体情報と本人確認書類で本人認証を行い、電子署名したとしても。
今も実務上、公証人が関与しているはずの公正証書遺言でさえ
「これが本当に本人の意思?」という内容の遺言に遭遇することがあります。
遺言を作りやすくなれば
それに伴い、制度を悪用する人が増えるかもしれないという懸念もありますね。
早めに遺言について考えておきたい方は、どうぞ遠慮なくご相談下さい。