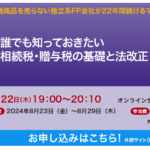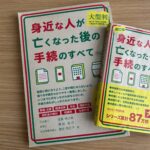国税庁は、10月28日に「相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集」などを公表しました。

相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集
この「相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集」では
間違いやすい事例を具体的に挙げて、正しい取扱いを解説してくれています。
事例① 被相続人の兄弟姉妹が相続した場合
事例② 被相続人の孫が相続した場合
事例③ 被相続人の孫が相続した場合
事例④ 被相続人と養子縁組を行った孫がいる場合
事例⑤ 生命保険金とともに払戻しを受ける前納保険料
事例⑥ 被相続人以外の名義の財産
事例⑦ 所得税の準確定申告書を提出し、還付金を受領している場合
事例⑧ 支給されていなかった年金を受け取った場合
事例⑨ 保険事故が発生していない生命保険契約
事例⑩ 保険事故が発生していない生命保険契約
事例⑪ お墓の購入費用に係る借入金
事例⑫ 未納の固定資産税・住民税
事例⑬ 団体信用生命保険契約により返済が免除される住宅ローン
事例⑭ 被相続人が亡くなる前3年以内の贈与財産
以上14事例について
どのように申告書に書けばいいか、書き方の「見本」も紹介されているので
(国の資料のわりには)一般の方でも分かりやすいです。
どういう場合が間違えやすいか
この事例を見ると、どういう場合に間違いが多いのか
その傾向も分かります。
・ 相続人が配偶者や子・親以外(2割加算や基礎控除額の計算)
・ 死亡保険金以外の生命保険関連
・ 名義預金
・ 生前贈与
・ 債務
などですね。
これらに該当する方は、関係のある項目だけでも、一度確認しておくと安心です。
相続税の申告のためのチェックシート(令和6年分以降用)
「小規模宅地等の特例」と「配偶者の税額軽減」を適用した相続税申告書の記載例
も、最新版が公表され
父が亡くなり、母と子ども2人の計3人が父の遺産を相続する際に
小規模宅地等の特例と配偶者の税額軽減を使う場合の
申告書の作成手順と記載方法が解説されています。
これに該当する方は多いので、自分で申告書を作る方はぜひ確認しておきましょう。
さらに、チェックもれがないか心配な方は
にも目を通しておくと、万全だと思います。