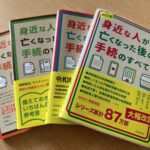先日、ある弁護士さんと税制改正の話になりました。
平成24年度の税制改正で「相続税の連帯保証人制度」が変わりました
今、話題になっている「消費税増税法案」、正式名称「社会保障の安定財源の確保等を図る・・・法律案(長いので中略)」は、実際には消費税だけではなく、所得税・相続税の増税も含むトリプル増税法案です。
この成立の見通しはまだ立たない一方で、あまり話題にならなかった平成24年度の税制改正は、既に可決・成立し、4月1日から施行済です。
相続税では「連帯納付の義務」=「相続税の連帯保証人制度」が変わりました。
本来、自分が負担する相続税は、自分が相続した財産に応じた分だけ、です。
でも、同じ人から財産を相続した人同士は、相続税という名の借金の、いわば連帯保証人になっています。
自分の払うべき相続税を支払わず、税務署の督促にも応じない不届き者がいたときには、その人の相続税まで払う義務が生じます。
連帯保証人にならなくていいケース
こんな不条理な制度が改正され、自分の相続税を期限までにキッチリ納めて5年たてば、もう他人の相続税の連帯保証人ではなくなることになりました。
また、相続税を期限までに納められず、分割払い(延納)している人の分は、最初から連帯保証人にならなくていいことになったのです。
そのため、弁護士さんからは
「それならなおさら、遺産分割でもめるなら”とことん”もめるべきですね。
福田先生は、10ヶ月以内に話し合いをまとめた方がいいと言われますが、
家族がいったんもめたら元どおりなんてありえない。
連帯納付の義務がなくなって、相続税の面からも相続人同士が一蓮托生では
なくなったのなら、弁護士に頼んでとことんやりあい、さっさと片付けたほうが
いいでしょう。」
と言われました。
相続税の連帯納付の義務がなければ、もめても大丈夫?
でも、連帯納付の義務はなくても、財産をもらう人同士、申告期限までに解決した方がいいことは、まだあります。
たとえば、亡くなった人が使っていた土地を8割引で相続できる「小規模宅地等の特例」は、事業用の土地の場合、10ヶ月以内に事業を引き継げるかがひとつのカギになるのです。
お医者様のご家庭で、実際に問題が生じたことがありました。
多額の弁護士報酬を支払った上、国に払う相続税まで増えてしまったとしたら、そもそも相続財産の全体額が減ってしまうことになります。
それって、とことん争ってもあまり意味がないのでは・・・。