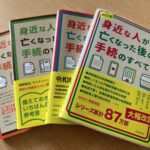相続税の増税に備え、生前のうちから子どもや孫へ、財産を贈与している方がいらっしゃるかもしれません。
「贈与税を納めていれば、それが贈与の証拠になる」は誤解!
「贈与税の申告納税がいらない年110万円以下の贈与ではなくて、あえて贈与税の税率が10%の範囲内、つまり、年310万円までの贈与を行って、税務署に贈与税の申告書を提出しておきましょう」と書かれている本を目にしました。
ただし、「贈与税の申告書を税務署に提出し、贈与税を納めていれば、それが贈与の証拠になる」というのは、大きな大きな誤解です。
たとえば祖父が、孫名義の預金口座に111万円を振り込んで、孫の名前で贈与税の申告書を作り、銀行の窓口で贈与税を1,000円納めれば、「これで税務署のお墨付き!」ではありません。
贈与契約書は作りましたか。通帳や印鑑を、祖父が保管したままではありませんか。
孫に渡し、孫が使うことができなければダメなのです。
贈与税の申告や納税だけは、贈与の証拠にはなりません。
申告や納税は、贈与の事実があると判断する、基準の「ひとつ」
「財産をもらったから・・・贈与税の申告書を提出し、税金を払います」。
「働いてお給料をもらったから・・・所得税や住民税が天引きされる」のと同じです。
「あげた」「もらった」がなかったり、もらった人が自由に使えなかったりするのなら、財産をもらったとはいえません。申告書や税金は、誤って提出された申告書であり、誤って納めた税金です。
お給料をもらった事実もないのに、所得税だけを払えと言われたら、払うでしょうか。それでは順序が逆です。
贈与の事実がないのに、贈与税を納めるのは、それとまったく同じことなのです。
ただし、税金を徴収する税務署の立場から見れば、申告や納税をしていることは、贈与の事実があると判断する、基準の「ひとつ」にはなります。
年間110万円を超える額の財産をもらったら、申告納税するのが義務です。
それすらしていないなら、贈与があったとは認めないでしょう。
「贈与の証拠の残し方」については、次回、ご説明したいと思います。